|
大動脈瘤とは―
大動脈は、心臓から拍出される血液を運ぶ重要な通路で、通常の太さは22ミリ程度です。高齢化と食生活の欧米化などにより、動脈が硬くなったり、もろくなったりするために内腔が拡大し、太くなって瘤状になった部分が35ミリ以上となったものを、大動脈瘤と診断します。瘤となって内腔が拡大した分、大動脈の壁が薄くなるため、血圧が急激に上がったりすると破裂する可能性が出てきます。一旦破裂すると大出血することから、救命は難しくなります。
瘤のでき方によって、大きく3つ(真性、解離性、仮性)に分類されます。真性大動脈瘤は大動脈壁の構造を保った状態で拡大したものであり、仮性動脈瘤は大動脈壁が全層、あるいは外膜の一部を残して破綻し、瘤壁が周りの構造によってかろうじて保たれている状態です。大動脈解離は大動脈壁が中膜の深さで解離し、腔が二腔となった状態です。解離発症から2週間以内であれば急性、それ以後は慢性と分類します。
発生頻度・原因
|
|
| 図1 大動脈瘤例のvon Mises応力分布:胸部下行大動脈瘤例のvon Mises応力の解析結果で、赤い部分が最も応力の高い箇所であり、青い部分が低い箇所に相当します。 |
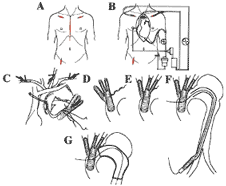 |
| 図2 ステントグラフトを用いた新しい弓部大動脈瘤の治療法:大動脈瘤内にステントグラフトを留置して内腔側より瘤を治療する方法です。 |
大動脈瘤の発生頻度は10万人当たり20〜30人/年であり、うち胸部は6〜10人/年、腹部は15―18人/年と、腹部大動脈瘤の発生率が高くなっています。また、死亡率や年間の手術症例数から推測すると、発生頻度は増加傾向にあります。
真性大動脈瘤の主な原因は動脈硬化症、動脈壁のコラーゲンおよびエラスチンの代謝異常、感染、炎症などです。また、解離性大動脈瘤は、高血圧症、二尖大動脈弁、先天性代謝異常、妊娠、炎症などが原因となっています。
男性は女性の3〜4倍多く発症し、50〜70歳の発症例が多くなっています。真性また解離性大動脈瘤の最大の原因が、動脈硬化また高血圧症であることから、大動脈瘤発症の主な予防法は高血圧の予防と食生活に注意する必要があります。
診断法・治療法
大動脈瘤は、病歴、胸部X線写真、超音波検査、CT(コンピューター断層撮影)検査、MRI(核磁気共鳴)検査、血管造影検査などで診断します。
治療法としては内科的治療と外科的治療があります。内科的治療は降圧療法と安静が主で、外科的治療としては瘤切除と人工血管置換術、またステントグラフト留置術があります。
これまで手術適応は主に瘤径で決定されており、このことは瘤径の増大とともに破裂頻度が高まることからも一理はあります。しかし、瘤径が50〜60ミリ未満で破裂する例も報告されており、瘤径とは異なるさらに信頼性と客観性の高い動脈瘤の診断システムが求められています。
私どもの研究室では、この動脈瘤の破断診断システムの開発をめざして、工学部生体機能工学分野・佐藤正明教授と共同研究を行っています。共同研究の初期はMRI画像に6ミリ間隔の格子を標識し、大動脈壁の動きを分析することにより大動脈のひずみを求め、大動脈瘤の好発部位と曲げ率、およびひずみとの関係、瘤の部位によりひずみが異なること、大動脈でひずみ分布が異なることなどを明らかにしてきました。最近はより精度の高い診断法を確立するために有限要素法を用いて、大動脈のCT画像から大動脈壁局所にかかる応力を求め、瘤の破断予測が可能かどうかを検討しています(図1)。
一方、最近の外科的治療法の特徴は、ステントグラフトを用いた低侵襲治療であり、私たちも図2のような新しい低侵襲治療法の開発を行い良好な結果を得ています。本法を用いることで心臓、呼吸、腎臓などの他臓器合併症を有する弓部大動脈瘤症例を、安全かつ低侵襲的に治療することが可能となってきました。大動脈瘤は高齢者に発症しやすく、また種々の他臓器合併症を有する例が多く、低侵襲的治療法の確立は今後の最大の課題と考えています。
|


