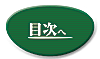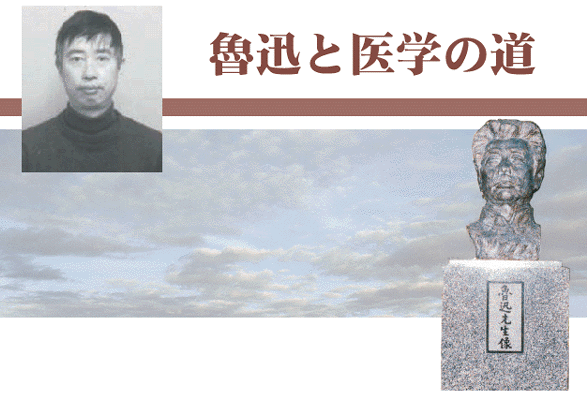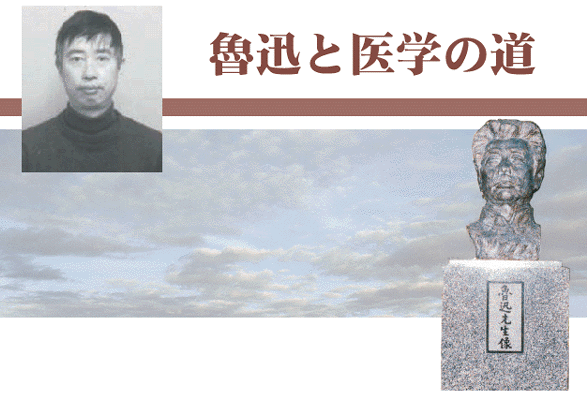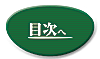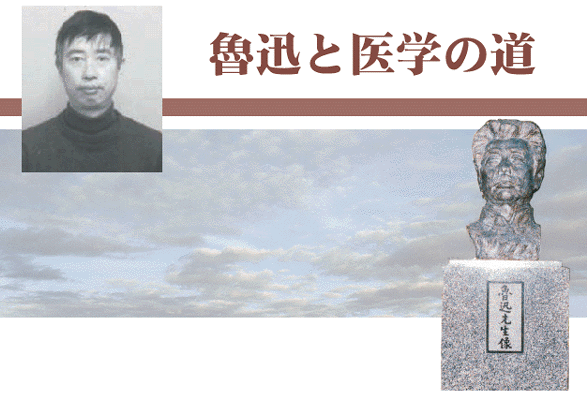
東北大学片平キャンパスにある魯迅像。
今でも学生達を見守っている。
母国の革命に
医学を役立てたい
魯迅は1904(明治37、光緒30)年9月に仙台医学専門学校に留学した。当時の日本は日露戦争の真っただ中で、仙台でも出征兵士歓送会や戦勝祝賀会などが、町内会組織を使って開催され、魯迅が下宿した「佐藤屋」の主人佐藤喜東治氏も、遼陽陥落の際の行列係の一員に名を連ねていたという。時代は日本が日清戦争から日露戦争へ、さらに朝鮮・中国侵略へと走り込み、清朝政府は武力を背景とした列強の強迫外交に対抗できぬまま、ずるずると餌食にされるばかりであった。
魯迅が日本に留学し、仙台医学専門学校に入学することになった背景には、中国の深刻な立ち後れがあった。例えば、日清戦争は、清国の軍隊が鉄砲の殺傷力には無理解で、勝敗が初めから決まっていたと、米国の新聞記者が報告している。また、人の死は気の衰退だから生き身の肉や血を使えば起死回生が可能であると信じられ、瀕死の父親に自分の肉を削いで与える孝行息子の話が伝えられていた。
魯迅が医学を選んだのは、生命の尊重や健康増進を追求する上に、西洋医学がいかに有益であるかを示し、人々の間に近代化を支持する雰囲気を広げていこうと考えたからである。また、医学によって中国人を人種的に強化していこうとも考えていた。ともに中国をよりよく変革するために、いいかえれば革命のために医学を役立てようと考えたのである。
真理探究の広がりへの
認識を深めて
仙台医学専門学校で、魯迅は藤野巌九郎教授に解剖学の指導を受けることになった。その指導は毎週ノートを添削するという徹底したもので、級友達も、しばしば添削を手伝うこととなった。その過程を通じて、魯迅は2つの大きな問題を認識するに至った。まず第1は、医学と革命を結合するのは、極めて困難であるということ、特に中国では、ことのほか難しそうだということである。第2には、近代的な学術は人類普遍的な真理を探究する営為であって、中国・中国人の問題を考える上にも、つまりは中国の革命を考える上にも、無視できない存在であると認識できたことである。
第1の問題では、ロシア軍スパイを働いたとかいう理屈で、1人の人間が処刑されようとしている場合に、中国人はそれを全く無表情に、まるで神経が麻痺しているかのようにぼうと眺めるばかりであり、その表情には、生命の尊重や健康増進を追求する意識は感じられない(「吶喊・自序」)、と思ってしまった。社会変革の土壌を切り開く上に、この中国人が相手では近代西洋医学はあまり役に立たない、魯迅はそう考えてしまったのである。また、医学で人種を強化できると考えたのは方法として間違いだったことにも気がついた。それは極めて苛烈な中国人観であった。
第2の問題は、藤野先生の厳格な指導の下で、解剖学の勉強をすすめる過程のなかで、藤野先生と魯迅の間の衝突や軋轢として、まず起こってきた。
当時の魯迅は、藤野先生によって解剖図と芸術絵画とは筋合いが違うと指導され、考えれば当然なのに、ひどく不満に感じたり、藤野先生から纏足の状態に関する説明を求められて大変困惑したり(「藤野先生」)と、自分の感覚が非学術的なばかりに受ける叱責や指導、困惑の事例を作品の中に提示している。その記述はまた、魯迅が近代学術に対する自分の認識が徐々に進む様子を描いたものでもあった。そしてついに、藤野厳九郎先生の指導によって、自分は中国よりも大きい学術の世界がある、人類普遍的な真理を探究する世界がある、ということを教えられたし、藤野先生はそれを自分に、また中国に伝えようとしたのだろうと語っている(「藤野先生」)。
魯迅と藤野先生の
勉学に傾けた熱意
魯迅の足跡を展望すれば、東北大学医学部は、その前身の仙台医学専門学校時代に、研究教育活動の上で、とても大きな国際貢献をしていたことになる。
それにしても藤野厳九郎先生の頑固さは、受講生を等しく苦しめたところのようである。魯迅の解剖学ノートの驚嘆すべき綿密さと、添削の多さを眺めると、こと勉学では幼い頃から貫き通してきた魯迅の完璧主義者ぶりと、「田舎の鈍才」的な藤野先生の基礎学に対する強烈な迫力のようなものを、門外ではあるがひしひしと感じさせられて、まさに身の引き締まる思いがするのである。
阿 部 兼 也=文
あべ けんや
1937年生まれ
東北大学名誉教授
東洋大学文学部教授